6/Ⅲ.(日)2011
新百合ヶ丘で、立川流一門会。この日は、志ら乃という志らくの弟子が前座で、談笑・志らくと続いた。
談笑の落語は変態的なギャグが満載で、2011年現在、中学生男子に1番受ける落語家じゃないかな。
志らくは、「志の輔・談春・志らく・談笑を談志四天王と呼び、志の輔・談春をA面、志らく・談笑がB面と言われています」と客を笑わせ、「でも、ヒット曲はA面から出ますが、名曲はB面にあったりします」とうまいことを言っていた。
志らくは、「楽太郎が‘円楽’を、いっぺいが‘三平’を継いで、そのうち花禄を‘小さん’と呼ぶ時代が間違いなく来る」、と断言し、「でも立川談志の名前は誰も継げない。いくら西田敏行が人気があっても渥美清の名前は継げないのと同じで、いくらジョニー・デップがいい演技をしても2代目・ポール・ニューマンと言ったら‘何を言ってやがんだ’となる。 それと同じ、談志を継ぐのは無理。いっそキウイ(弟子の中で、ものすごく前座期間が長かったことで有名)にでも継がせるか」と笑いをとった。
談志は深緑の紋付に緑色のバンダナで登場、‘長屋の花見’を演じる。「短いから、サービスでもう一席」と‘蜘蛛駕籠’をやった。
相変らず、声が出なくて咳を頻回にするのだが、その度、「俺の咳を拾うためにマイクロフォンがあるんじゃないよ」、「○×の薬は効かないよ」と言い、大きな長い咳の後には、「これで死んでしまえば、いい終わりを観たってことになるね」と言って笑いを誘った。
談志は、「昔、‘円歌・志ん朝2人会’で、志ん朝が倒れたから、変わりに行ってくれと頼まれたことがある」という思い出を話し、高座に出て「円歌がわずらったんなら、客は喜んだろうな」と言ってやったんだと自慢した。明日、円歌と対談らしい。
でも、談志は、「あいつ(志ん朝)とは2人会をしたことはない。円楽とも、2人会はないな。志ん朝も円楽も死んじゃったな」とかすれた声で言った。
談志は長生きの家系で、母親は95才で元気で老人ホームにいて、見舞いに行くと、「泊まってけ、泊まってけ」と言うそうだ。<どっから来たの?>と聞くが「根津」と答えても判らない。<どっから来たの?>「根津」。<どっから来たの?>「根津」。何度言っても判らないから、「ねずねずねずねずねずねずねずねずねずねずねずねずねずねずねず…」って言ってやったら、<あぁ、根津か>と答えるんだという。そんな話もしてた。
新百合で談志をみるのは、2度目だ。1度目は、談志に癌がみつかった直後の落語会で、ワイドショーのレポーターがいっぱい取材に押し寄せて来てた。その日の談志の演目は、‘居残り佐平次’だった。

‘居残り佐平次’を、ある落語評論家は「落語の品位を落としている」作品というが、談志は、これこそが落語の料簡だ、という。
談志は、落語とは人間の業の肯定だ、という。それはどういう事かと言うと、人間とはそもそもだらしなく、いい加減な者なのだ。
でも、それでは世の中が成り立たないから、常識というルールを作り、それを子供の頃から押し付けられて生きる。
それは仕方のないことである。でも、それには無理がある。落語は常識ではなく非常識を語ることで、その無理を語り、時にはそれから解放してやるのが落語の役割なのだ、というのが談志の落語の定義なのである。
佐平次は、人生成り行きと決めつけ、金もないのに何人も引き連れ女郎屋でさんざん飲み食いし、夜中のうちに連れを帰し、自分が居残りをする。
居残った後もまるで反省の色はなくいい加減の限りを尽くすが、これが全部うまく行く。努力も苦労も悩みもしないで成功する。それこそ、コツコツやる奴ぁ~ご苦労さん!の世界だ。その非常識さとバイタリティーには大いに憬れる。
川島雄三というカルト人気のある映画監督が、フランキー堺・主演で『幕末太陽傳』という映画にもしている。日本の喜劇映画の最高峰の作品だから、機会があったら観るといいと思う。シロクロだけど、面白いです。
その『幕末太陽傳』でも、落語の原作でも、佐平次は肺病を患っている、という設定になっている。
単にいい加減な奴が成功してはしめしがつかないからリスクを背景に作ったのか、あるいは究極的な非常識を体現できるのは死と対峙した者だからこそ達した境地とでもいいたいのか。そうでもないと、世間のルールと辻褄が合わないのは確かである。
しかし談志は、佐平次を肺病にしなければいけない理由が判らない、と、談志の落語では、佐平次が肺病だという描写はない。「人間の業の肯定」のための「交換条件」を不要と判断したのだろう。
ところが、談志は癌になった。癌を患った談志が、‘佐平次’を演じる。命をかけて悲壮なまでに「いい加減」を演じる談志。まるで、ジグソーパズルの最後のピースがおさまったみたいで、談志は、この日のために佐平次を病気にしないでとっておいたのではないかとさえ勘繰りたくさえなった。
その迫力たるは、背筋がゾッとした。今、目の前で繰り広げられてるものこそが、「居残り佐平次・完璧版」なのだ。
その日に立ち会えたのは、僕にとっては今では勲章のように思っている。1997年のことだ。もう14年になる。
談志、不死身か?。
BGM. ザ・リリーズ「好きよキャプテン」
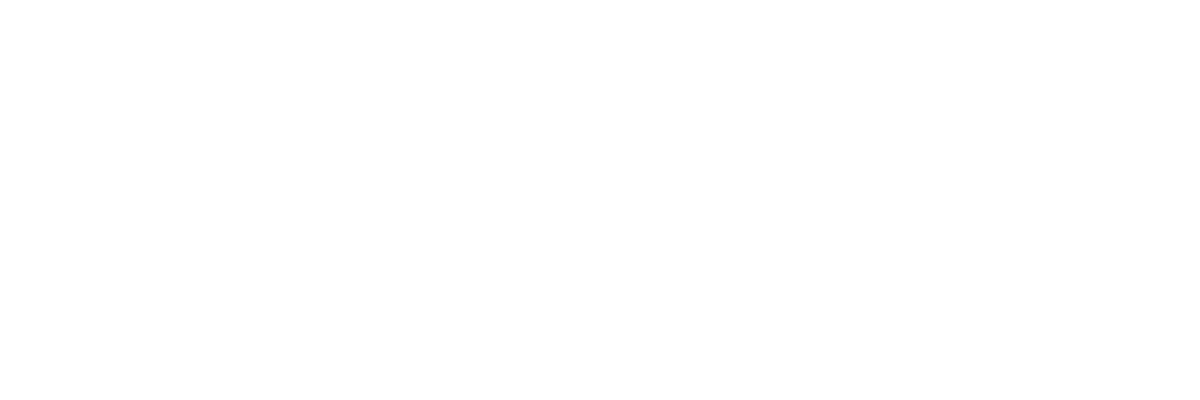
精神科一般 思春期相談/家族相談