25/Ⅰ.(金)2019 はれ、寒い かいせさん、髪を切る
以前に書いた記事だが、これはよく聞かれる質問なので、コンパクトに、短くして再録してみる。
↓
僕の家は眼科の開業医で、僕は二人兄弟だったから、将来は、父と兄と3人で医院を大きくすることが刷り込まれていた。
周囲の誰もがそう思っていたし、それをやっかむ人もなく、暖かく見守られていた。
そういう時代だった。
それは仕方がなかった。
こればかりは個人の力ではどうしようもなく、僕は物心付いた時から、医者になることになっていた。
勿論、その後の人生で、思春期や反抗期で、それを修正する機会は平等に与えられた。
だけど、僕は医者になった。
それは医者になる、のではなく、精神科医になろうという強い意志があったのだ。
医者になるには医学部に入り、全教科を勉強して、全教科の国家試験をパスしないといけない。
だから、逆に言えば、医師免許があれば、何科にでもなれた。
僕にとっての将来の約束は、医者になることだった。
親の都合は、家の眼科を手伝うことだった。
しかし、拡大解釈をすれば、医者になれば何をやっても良いとも言えた。
僕の親族には医者が多かったから、僕は専門的に色んな科があることを知っていた。
ここまでが前置き、ね。
僕の生まれは湘南の茅ヶ崎の海側で、そこは別荘地の多い温暖なゆったりとした風土だった。
僕が幼稚園の頃、近所をブツブツと独り言を言いながら、乳母車を引いている貧しい老婆が徘徊していた。
老婆は乳母車に古い赤ん坊の人形を乗せていて、その人形を本当の赤ん坊だと思っているという噂だった。
すずめ、を捕まえて食べてるという噂もあった。
僕は母親やお手伝いさん達に、「タッちゃん、あの人に話しかけてはダメですよ」と教えられていた。
ある日、狭い路地で、乳母車の老婆と鉢合わせになった。
僕は思わず、<すずめ、って食べれるの?>と聞いた。
すると、老婆は「坊や、そんな可哀想なことをしてはいけないよ」とビックリするほど、優しい声で言った。
僕は一瞬で、この人は良い人だ、とピンと来た。
すると、そんな気持ちが以心伝心、彼女にも伝わったらしく、僕らは仲良くなった。
老婆は乳母車から赤ん坊を抱え上げて、「ほら、こうするとお日様が透けて見えて綺麗なんだよ」と僕に教えてくれた。
セルロイドの人形に夕陽が差し込んで、それはキラキラと反射して輝いて虹のように見えた。
しかし、僕はこの事は、親には秘密にしておいた。
同じ頃、似たような事件があった。
僕の実家は診療所の2軒隣りにワンブロックほどの広さを持っている大きな家だった。
だから、時々、「乞食」(←これは不適切な表現なのでしょうが、差別を助長する意図ではないので使用します)が来た。
母親やお手伝いさんは、「タッちゃん、乞食が来たら、食べ物をあげちゃダメですよ。クセになってまた来るから」と言った。
僕は言う通りにしていた。
ところが、ある日、僕しか家にいない時に、勝手口から、女の乞食が、「何か恵んで下さい」と入って来た。
僕は、<お前に、何かあげるとクセになってまた来るから、やらない>とピシャリと言い放った。
すると女の乞食は、「坊ちゃん、もう何日も何も食べてないのです。約束します。今日だけですから」と懇願した。
僕は女乞食の目をジッと観察して、僕にはこの人が嘘をつくようには見えなかった。
そこで、従業員がいつでも、食べれるように台所に置いてある塩むすびを持って来てあげた。
女乞食は何度も何度もお礼を言い、約束は守る、と言って帰って行った。
僕はこの事も、大人達には話さなかった。
代わりに、毎日、<ねぇ、今日、乞食、来なかった?>と聞くのが日課だった。
すると、親やお手伝いさん達は、「変な事を気にするのね。乞食なんか来ませんよ」と笑った。
女乞食は僕との約束をちゃんと守ったのだ。
僕はこれらの事を通じて、大人たちの言う事はなんていい加減なものだろうとあきれた。
そして、こういう「常識」とか「普通」は疑ってかかる必要があると思った。
当時の僕は幼稚園生だったから、実際はそんな風に言語化は出来なかったと思う。
今、振り返って、解説すると、そういうことだと言うことです。
僕はそれ以来、無批判にこの世を支配している「常識」とか「普通」とか「規則」とか「一般」とかを敵視するようになった。
それは、そういう事によって、無力な人が、抵抗する術もなく、不当に扱われてることに義憤を感じると同時に、
「常識」に縛られて、生きている大人たちも決して、自由に見えなかったからだ。
僕は将来、医者になったら、歪んだ「常識」や「普通」で窮屈をしている人達を助ける仕事をしたいと思った。
その頃の知識で、精神科という科があることを僕は知っていた。
僕は医者と言う権威を武器に、差別や誤解を受けてる人や、不自由に生きている大人たちの心を解放するために力を発揮しようと決めた。
そして、それは僕の性質上、とても向いているとも思った。
それが僕が精神科医になった訳で、この初心はブレることなく今に至っている。
BGM. よしだたくろう「今日までそして明日から」
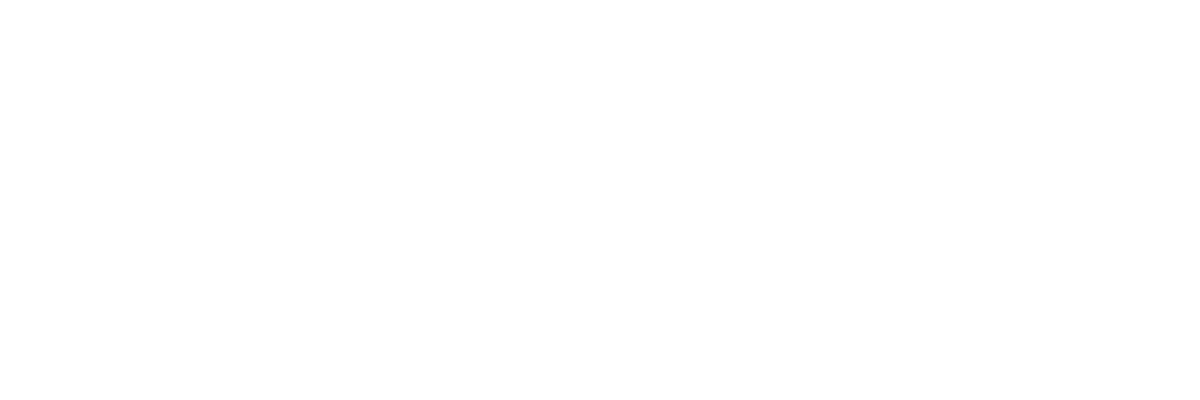
こんにちは。 連日で強い風が吹きます。その方角によって寒かったり妙に温(ぬく)かったりもしますようで。
昨年秋以来でしょうか、いわば【赤】系統の色合いで日々を過ごしておりましたが、昨日あたりからは【青】系統の色合いが感ぜられるように思えて来てもいます。移ろいゆく己というものを季節の移り変わりに例えて、そして捉えてみようかなどとも思いましたが。どうもしっくりとはいきませぬようで。
その昔、ジュリーも歌ってました。
『おちてゆくのもしあわせだよと』
・・・いまだに疑っています。 晴れる見通しはたっていません。
幼少期の感覚や体験を言語化するのは。
それらを継承してきた自らに課せられる、なんとも歯がゆい手段だなと感じています。『本当は、そんなんじゃなかった』と、文章にしてみて、会話の中で他者に話してみて、これまでに何度も感じて来たことでもあります。だからと言って、決してその限りでもありませぬ。そーゆーのは【相手のある】ことでもありますから。そんな相手なり、シチュエーションなりに救われていることも、きっとあるのでしょう。
P.S. 『いもジュリー』という言葉、知ってますか。
誰も覚えてナイと言うのです。 青年期・以来の疑問なのですが。
確か移動中の新幹線車内で乗客から”そう揶揄されて”暴力沙汰
となっていた?ような気がするのですが。
私の幼少期の記憶なんて こんなもんですょ。
散文気分さん、こんにちは。
いもジュリー事件、勿論知ってますよ。
新幹線の中で男に「いもジュリー」とイチャモンつけられたジュリーは、相手のタマキン握り潰して頭突き食らわした、って事件でしょ?
ジュリーは長髪で中性的なファッションだったけど、「すげ~、ジュリー!」って中学の教室で大騒ぎした思い出があります。
猪木とモハメッド・アリが異種格闘技戦をやるってザワついてる頃の出来事ですよ。
その年の暮れに、猪木は敵地パキスタンでパキスタンの国民的英雄アクラム・ペールワンの腕をガチンコで折りました。
「いもジュリー事件」と「猪木腕折り事件」が僕にとって忘れられない、1976年の2大暴力事件です。
私も多分家にそのような感じできたら、何か渡すと思います。
親の言ってる事もわかるけど、子供なりにもう二度とこないと言っている人の見わけはなんとなくわかるのではないかと思う・・・
でもそんな親切心を利用して誘拐や、犯罪が増えているのが今の日本。
純粋な子供の心を素直に育てにくい環境になったものです。
sinさん、こんにちは。
カトリック系の幼稚園が教育を困っているそうです。
汝の隣人を愛せよ、ではなく、知らない人には近づかないこと、って教えないといけないから。