僕が大学院を出て出向してた病院の話だから、僕が精神科医になって7~8年目の頃で30代の前半の年齢だった。
その病院には色んな大学病院から精神科医が出向して来ていたし、教授クラスの名の通った偉い先生もたくさんいた。そこで切磋琢磨出来たのは貴重な経験だった。
当時の僕はちょっと天狗だった。精神科の場合、外科などと違い「オペの件数が何件」などという分かりやすい実力を示す指標がなく、「教授が治せなくても研修医が良くしちゃう」というビギナーズラックが存在したから勘違いしやすかった。
その病院で「偉い先生」が手を焼いている妄想型分裂病(当時はそういう呼び方をした)の患者がいた。彼は行く先々で「喪服の男女にまちぶせられている」という追跡妄想のみが症状としてあって、それ以外は「正常」であった。だから家族も主治医もなんとかその妄想を説得しようと必死になり、最終的にはブチ切れて彼に不信感を抱かれ治療が進まなくなってしまった。
そこで僕に白羽の矢が立った。この膠着状態をなんとか和らげて欲しい、と僕がサブのペア・ドクターとして担当についた。僕に言わせれば、分裂病の妄想である。そこで有効な精神療法は「支持・傾聴・共感」である。つまりよく話を聴き、相手を否定せず、彼の心の中で起きてる「心的現実」に共感して、寄り添えば治療関係は結べる。そんなことは教科書に書いてあるじゃないか。それなのに、「偉い医者」は家族なら仕方がないが一緒になって患者の妄想を「現実原則」として真っ向から否定するからそりゃ信頼関係もあったものではない、と腹の中で軽蔑した。
それからどうなったかというと僕の治療戦略はピシャリとハマって、患者は僕に心を開き、治療者・患者関係が築け患者は嫌がっていた薬も服用するようになった。薬は妄想には効くには効くから、彼の追跡妄想は遠隔化して行った。
そんな時だった。僕は夢をみた。町の中でどこへ行っても「喪服の男女がいて」僕を先回りして追い回して来るのである。僕は叫び声と同時に目を覚まし、ものすごく怖かった。彼が体験している世界観がそこにあった。
僕は急いで身支度をして病院に着くなり真っ先に彼の元に行った。そしてこう言った。「僕は正直、あなたの言う事を、わかるわかる、と聞いていたが、それは他の人がやらないから僕だけはそういう立場でいようと思ってやっていた。しかし、今日、こんな夢をみて、それは恐ろしくて今でも動悸が収まらない。僕はあなたに謝らなくてはいけない。今まで分かったふりをしてただけで、実際、体験したらこんなに恐ろしいものだとは想像したこともなかったからとても不誠実だったと思う。すごく申し訳なかった。ごめんなさい」と頭を下げると、彼はすごく優しい表情で包み込むような声で僕にこう言った。
「先生、それは怖かったでしょう」
僕はその声を聴いた瞬間にさっきまで鳴りやまなかった動悸が消えた。「共感」というものの持つ偉大な力をその時にはじめて知った。
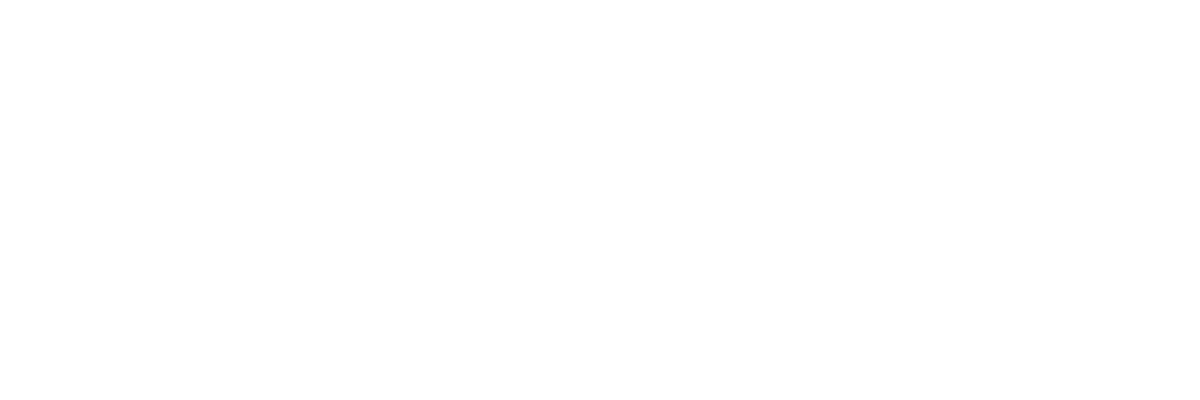
皆さん、勘違いしているんですよ。精神病患者は、そうじゃない人もいるんでしょうが、たいてい、みんな優しい人たちなんですよ。だって、共感と優しさに飢えているんですからね。自分の優しさを共に共感し合おうよって。
だから、誰かが手を差し伸べて、その人が精神科医であるとしたら、良い優れた精神科医なら、時間をかけて治療をして行けば、たいていは、症状も良くなっていくんじゃないですか。カウンセリングも含めて。
世の中、そう甘くはないけど、精神科に追い風は吹いている気がします。
川原先生は、優しいですね。時として厳しいけど、お説教された覚えがない。こちらの身になって、力説してくれたことはあった。患者の身になってくれますよ。
昔のボクシングマンガ「あしたのジョー」、もし、主人公の矢吹丈にオッちゃんがいなかったら、葉子さんがいなかったら、力石徹がもしいなかったら。どうなっていたか。
そんなことを思ったりしますよ。古い例で恐縮ですが。
ぴぴさん、こんばんは。
確かに、多くの人は勘違いしているのかもしれませんね。「啓蒙活動」も我々の仕事だから頑張って行きたいです。
ぴぴさんからの目線と言うか、アドヴァイスありがとうございました。僕らがやれることもまだまだあると思いました。
精神科やカウンセリングがもっと身近に利用できるような世の中になると良いなと思います。
「あしたのジョー」の喩は分かりやすいです。ま、年齢もあるのでしょうね(笑)ではまた~
なんだか映画の序章のようで、圧倒されてしまいました。
以下、護美箱つぶやきです。
めろんのめさん、こんにちは。
共感って専門用語だと、エンパシーって英語なのです。「〜パシー」って、瞬時に伝わるって意味らしく、テレパシーと同じ意味合いだそうです。
だから、考えや動作やシチュエーションや戦略が入るのは「質の悪い共感」で、今僕らがディスカッションしているテーマは、「質の良い共感を生じさせるための工夫は何か?」なのですよ。
共感によく似てて違うものに、共鳴とか同情とか共振れ、とかがありますね。そこら辺をごちゃごちゃに使ってる人もいて、我々の業界では。
そのくらい、「共感エンパシー」って定義が難しいのです。皆んなが使うから、手垢がついて、皆んな違う意味で同じ言葉を使ってるから一回、整理しようとしてる最中なのです。
そんな時に書いた記事なのです。ではまた~